Our Love’s In Danger ベースコピー譜
Our Love's In Danger ベースコピー譜
| 再ダウンロード有効期間(日数) | 無期限 |
|---|---|
| ファイル名 | Our Love's In Danger(Anthony Jackson).pdf |
| 公開日 | |
| バージョン | 1 |
| 制作 | 納浩一オンラインショップ |
- 商品詳細説明
- 商品レビュー( 0 )
「ベーシスト列伝」の二人目はアンソニー・ジャクソン
第1回目のポール・チェンバースのときにも触れましたが、回ごとにアコースティックベース奏者とエレクトリックベース奏者を、交互に取り上げたいと思います。
どちらも演奏するベーシストは、スペシャル枠とでもしましょうかね?
それはさておき、そんなことで今回はこの方を取り上げました。
ではそのアンソニー・ジャクソンの基本データです。
生年月日:1952年6月23日
出身地:アメリカ ニューヨーク
僕自身が影響を受けたベーシストと3人挙げろと言われると、エレクトリックベースに関しては次のベーシストになります。
ジャコ・パストリアス、マーカス・ミラー、アンソニー・ジャクソン
これまでに、このサロンでも、またその他のいろんな雑誌やクリニックなどでも、僕はジャコとマーカスから大きな影響を受けたことは、もう何度も触れてきたように思います。
しかしながら、今現在、実際の演奏中に「ああ、今この瞬間、あんなフレーズを弾きたい!」、あるいは「あんなアプローチをしてみたい!」と自分の頭の中に浮かぶ、そのフレーズやアプローチが、実はアンソニー・ジャクソンのそれであることが、ジャコやマーカスのそれより、遙かに多い気がしています。
まあ、ジャコやマーカスのアイデアは、それを実際の演奏で使うと、あまりにネタバレになってしまうので、僕のなかでは完全に封じ手になっていますが。
もちろん、ジャコやマーカスに限らず、アンソニー・ジャクソンのアイデアも、そう簡単には現場でうまくはまるわけではありませんから、そこは僕なりの解釈やアレンジでの処理をしていますが。
いずれにしても、それほどに、今の僕の頭の中には、アンソニー・ジャクソンのサウンドが渦巻いています。
この人は、伝え聞くところによると、「超」の文字が付くくらい、こだわりの方かと思います。
例えば、ジャズライフ誌での彼のインタビューの時、インタビュアーは僕の知り合いのベーシストだったのですが、「あなたはベースを弾くときに…」と質問するたびに、「僕が弾いているのはベースではない。コントラバス・ベース・ギターだ!」と、何度も言い直させられたと聞きました。
そう、彼が弾いているのはベースでなく、ギターなんですね。それがたまたま、普通のギターより低域に設定されているという発想のようです。まあ、そう言われてみると、そんなような気もしますね。
そういえば、今回載せたコピー譜の「Our Love’s In Danger」(アルバムはチャカ・カーンの「Naughty」)での演奏も、全編、ピック弾きによるものです。
彼はそのキャリアは、12歳くらいの頃に手にしたギターから始まったらしいので、だからベースをピックで弾く奏法も、自然と取り入れたんでしょうね。
それにしても、ピック弾きによる相当エッジの立った音に、さらにフランジャーをかなり強めにかけるというこの独特のサウンドは、当時、本当に斬新でした。
アンソニー・ジャクソンはこの頃は、4弦のフェンダー・ジャズ・ベースを弾いています。
この曲でも、フランジャーをバキバキに強めにかけてピック弾きで演奏しています。
このオクターブのフレーズなんか、なんともいえずファンキーで良いですよね!
これぞまさに、アンソニージャクソンのサウンド、そしてグルーブかと思います。
(ちなにこの「Our Love In Danger」のアルバムは1980年の録音ですが、そこに入っている他のベーシストがまた凄い!
アンソニー・ジャクソン以外に、ウィリー・ウィークス、そしてまだ若干21歳のマーカス・ミラーです。
マーカスは、まだサドウスキーが彼のベースのサウンドをいじる前の頃の音です。こうやって聞くと、演奏は今のマーカスですが、サウンドは、いわゆる普通のフェンダー・ジャズ・ベースの音ですね。なんか、マーカスにもこんな時代があったというのが判るという意味では、貴重は音源かもしれません。)
それ以外にもこだわりは多岐にわたっています。
彼はまず、絶対に立って演奏しません。たとえ何があろうと座っています。
歳を取ってしんどくなったからなのではなく、もう20歳代の頃から座っています。
TouTubeに、チャカ・カーンの1981年6月7日の「Roxy Theater」でのライブの映像が出ています。彼が29歳の時ですね。この映像は、僕も若いときに、何度か目にしたのですが、とにかく凄いサポートメンバーですし、チャカ・カーンももっとも売れていた時期ですから、ご機嫌な超ヒット曲のオンパレードの映像なので、本当に大好きなライブ音源です。
ちなみにメンバーは、ブレッカー兄弟、スティーブ・フェローン、デヴィッド・T・ウォーカーらが参加しています。
もちろんベースはアンソニー・ジャクソンなので、こんな映像があることを知ったときは、まだ見ぬ彼の演奏の模様を見たくてワクワクしたことを覚えています。
が、アンソニー・ジャクソンは、その強力な音こそ聞こえるものの、姿形はどこにもありません。
「ん? なんでやねん? まさか、クレジットミス? でもこの音もプレイも、彼以外の何物でもないしなぁ…」ということでよく見ていると、数曲たった頃から、彼だけがステージの後ろの方で座っているので、譜面台に隠れて全く見えない、ただそのベースのネックだけが、ほんのたまにかろうじて見えることに気づきました。
なんと、こんなイケイケの、しかもこんなメンバーの囲まれた中でも、絶対座って演奏するんですね。
もちろん、今となっては、彼は絶対立って演奏しないことは周知の事実となっていますが、この1981年当時は、世の中にYouTubeなどもなく、その実際の演奏シーンを目にすることなど本当にレアだった時代ですから、彼は終止、座って演奏するということなど、想像する由もありませんでした。
「この人、なんか、足でも悪いのかなぁ?」と、最初は思ったくらいです。
念のため、証拠写真を添付しておきます。
まあ、演奏内容は素晴らしいので、是非見てみてください。
参考動画
(Chaka Khan – Live at Roxy 1981年
同じ頃の映像で、もう少し、彼がしっかりと画面に現れるものもあります。
グローバー・ワシントン・ジュニアが、彼のアルバム「Wine Light」で大ヒットしたときのライブの模様です。
アルバムではマーカス・ミラーが弾いていますが、このライブはアンソニー・ジャクソンです。
4弦のフェンダージャズベースを弾いていた頃の貴重な映像です。
Grover Washington Jr. In Concert 1981年
実は僕が大学に入って本格的に音楽を志しだしたとき、初めて手にしたベースは、彼の4弦のフェンダージャズベースに憧れて、ESPで特注してもらったものでした。
それくらいに、昔から好きだったんですね。
さて、もう一つの彼のこだわりは、絶対にスラップをしないことでしょう。
彼自身、インタビューで、「昔はそのために、仕事を断られたこともあったような気がする」といってましたね。
しかし、それならこのチャカ・カーンのライブも、よく断わられなかったものですね。
だってライブ映像の収録なのに、一人座っているわけですからね。でも、そんなビジュアルの問題以上に、彼はその演奏スタイルが大事だったんですね。いやはや、ほんと、おみそれします。
こだわりという点でいえば、さらにあります。
今回のコピー譜を載せたこのテイク、あとでこのアルバムの録音裏話みたいなものを、どこかで読んだことがあるのですが、この曲に関して、アンソニー・ジャクソンは、誰が聞いても完璧と思えるその演奏のどこかが気に入らないらしく、「ちょっと持ち帰らせてくれ。」といって、一人で徹底的に、細かな部分を修正してきたそうです。
そういえば、日本を代表する大先輩、今はもうお亡くなりになりましたが、テナーサックス奏者の松本秀彦さんのレコーディングに、彼が参加したときの話も聞きました。
そのときのピアニストは、僕も本当によく知っている青柳誠さんだったのですが、彼が教えてくれた話によると、曲の演奏が終わってみんなでプレイバックを聞いたとき、もう誰が聞いても文句の付けようもない演奏なのに、「ちょっと直させてくれ。」といって、一人、ベースのブースに入って、黙々と修正していたそうです。でもやっぱり、誰が聞いてもどこが悪いのか判らない。
きっと本人にだけ、その気に入らない部分が判っていたんでしょうね。
いやはや、もうそのこだわりようといったら!
では最近の彼のプレイスタイルに関して、触れておきたいと思います。
僕が彼の演奏でも、特に好きな作品が、ミシェル・カミロのビッグバンドでのライブアルバム「Calibe」での演奏です。
このアルバムには、なんと同じ音源でのDVDも付いているので、彼のプレイも、映像で堪能できます。まあ、1994年の音源なので、「最近の」とはいえませんが、彼自身のプレイスタイルは今とほとんど変わっていませんので、彼のスタイルを語る時の参考にしても差し支えないでしょう。
とにかく彼の演奏で、僕が気に入っているのは、そのフィルインです。
フィルインを入れるタイミングやそのフレージングが、他のベーシストとは全く異なります。
その片鱗は、今回取り上げた曲「Our Love In Danger」の中でも爺所に出てきます。
多くの場合、高音域から一気に降りてくるようなフレーズで、それだけでも耳を奪われるのですが、その音使いも絶妙かつ摩訶不思議。一体どういうスケールを使っているのか、よくわからないフレーズがよくあります。
僕が、自分自身の演奏中でも、「アンソニー・ジャクソンみたいに弾いてみたい!」という感じでよく耳に聞こえてくるのが、このフィルインなんですが、あまりに彼独特のタイミングとフレージングで入ってくるので、どうやってもなんな感じないはならないんですね。
(これに関しては、同じ事がジャコにもいえます。
彼が入れるフィルインも、あまりに絶妙なタイミングで、しかも独特の音選び。
これを真似すると、一発で「あっ! ジャコのフレーズ!」ってばれてしまうというのは、ジャコが好きなベーシストなら、きっといやというほど経験していることでしょう。)
そのフィルインを可能にしているのが、はやり彼のトレードマークともいえる、6弦ベースですね。相当高い高音域から一気に降りてくることが出来るので、彼のフィルインを可能しているのでしょう。
次に挙げたいのが、右手を使ったミュートサウンドと、そのときに使う右手の親指でのピッキングです。ぼくはこのサウンドが大好きで、自分の演奏中でも、かなりの頻度で使っていますが、アンソニー・ジャクソンのようなスピードでは到底弾けません。一体どうやって、親指だけであんな高速フレーズを弾くことが出来るのか、さっぱり判りません。おそらくは、ギターのように、他の指も使っての、いわゆるギターのフィンガリングのようにしているのだろうと思います。
実は僕も、ベースを始める前にちょっとだけギターをしていたので、いまもミュート奏法の時に、ギターのような3フィンガーで弾くことがあります。きっとそれでしょうね。
彼のサウンドも本当に独特なんですが、それはやはり彼の使うフォデラによるところが大きいのでしょう。
昔、ベースマガジンの特集で、たくさんの6弦ベースを試奏したときに、フォデラのアンソニー・ジャクソンモデルをを弾いたことがありましたが、それはもう、びっくりの連続です!
まず36インチという大きさ。僕のように、体格のない人間には全く演奏不能なほどのでかさです。
しかもフレットは28フレットまであるのですが、そこには一つのフレットマークもないので、僕のようにそれを頼りに弾いているベーシストには、特に高音域での演奏の場合、一体今自分が第何フレットの何ポジションを弾いているのか、さっぱり判らなくなります。
つまみも、ボリュームしか付いていないので、音色の変化をベース側で調整することは全く不可能です。ところが実はアンプの方でも音色の変化を調整することが出来ませんから、結局すべては指で付けることとなります。
というのも、最近はどんなアンプを使っているのか定かではありませんが、僕が知っている10年以上前、彼のアンプは確かEQなどのつまみが全くないヘッドアンプで、それにケーブルを直接つないでいたようで、アンプの方でも特にイコライジングは全く出来ないような仕様になっていました。
まあ、彼はインタビューでもいっているように、彼が自分の目指すサウンドとしてイメージしている楽器は、リュートのような古楽器だそうですから、そんな楽器につまみが付いていないのは当たり前ですからね。しかし不思議な人ですね。
その代わりといいうことでしょうか、彼は足下に置いているボリュームペダルを多様することによって、様々は音量に変化を付けています。例えば、フレーズの最初の入り口だけ小さい音にし、そこからフレーズが進むにつれてボリュームを上げるというような、いわゆるギターでいうところのボリューム奏法のような効果を出したりします。これがまた不思議な雰囲気を醸し出すのですが、こんなことをするベーシストは、彼以外に誰もいません。
このあたりも、彼の独創性が垣間見えますね。
グルーブに関しても、本当に独特です。
一つ一つの音は実に正確に、そして明確に出ているのですが、全体としては独特のうねりがあります。その意味でも、あのグルーブ感が、一体どのように作られているのか、これまたさっぱり判りません。まさに彼独特をいわざるを得ません。でもとにかく正確無比であることは、もう驚くレベルです。
このように、そのサウンド、グルーブ、そしてそれらを生み出した彼のこだわりの強さ等々があまりに個性的である故、彼のスタイルを継承するようなベーシスト、いわゆるアンソニー・ジャクソン小僧のようなベーシストは、未だに一人もいないと思います。
あまりに個性的なんですね。きっと、楽器を始めた頃からのその練習方法も、楽器に対する考え方も、全く他のベーシストとは違ったんでしょうね。
そのことは、僕のもう一人の大好きなベーシスト、スティーブ・スワローにも通じます。
彼のこともまた、またこの「ベーシスト列伝」で触れたいと思います。


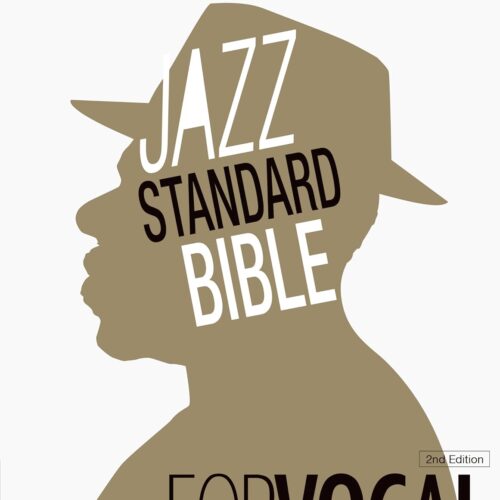 ジャズ・スタンダード・バイブル FOR VOCAL 2nd Edition
ジャズ・スタンダード・バイブル FOR VOCAL 2nd Edition ジャズ・スタンダード・バイブル in B♭ ハンディ版 セッションに役立つ不朽の227曲 開きやすいリング綴じ CD付き
ジャズ・スタンダード・バイブル in B♭ ハンディ版 セッションに役立つ不朽の227曲 開きやすいリング綴じ CD付き Whims Of Chambers ベースコピー譜
Whims Of Chambers ベースコピー譜 ジャズ・スタンダード・バイブル 2 改訂版 in B♭ セッションをもっと楽しむ不朽の名曲選 CD付き
ジャズ・スタンダード・バイブル 2 改訂版 in B♭ セッションをもっと楽しむ不朽の名曲選 CD付き