Hesitation by Ron Carter ベース譜
Hesitation by Ron Carter ベース譜
| 再ダウンロード有効期間(日数) | 無期限 |
|---|---|
| ファイル名 | Hesitation(Ron Carter).pdf |
| 公開日 | |
| バージョン | 1 |
| 制作 | 納浩一オンラインショップ |
- 商品詳細説明
- 商品レビュー( 0 )
このコーナーではアコースティックベース奏者とエレクトリックベース奏者を交互に取り上げようと思います。前回はアンソニージャクソンでしたので、今回は、いまも現役で活躍中の、アコースティックベース奏者、ロン・カーターを選びました。
今回は、ジャズ入門講座伴奏編第6回として「循環曲への対応」とのコラボ記事とさせてもらいますので、もしそちらの方もご興味があれば、是非一読ください。よろしくお願いします。
ではロン・カーターの基本情報です。
生年月日:1937年5月4日
出身地:アメリカ ミシガン州
現在は82歳ですが、毎年のように日本に来日して、演奏活動をされています。凄いですよね。
彼のキャリアで、やはり最も特筆すべきものは、マイルスデイビスの第2期黄金のクインテットでしょう。
1963年にマイルスのバンドに参加し、翌1964年に、そのマイルスバンドが日本初来日をしたようです。で、その年にサックスのウェイン・ショーターが参加し、ロン・カーター、ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、トニー・ウィリアムスの4人が、マイルスの第2期黄金のクインテットとなります。
この頃の映像は、YouTubeなどでもたくさん見ることが出来ますから、まだ見たことがないという方は一度見てみてください。
(以下のURLで見られます。
こちらは、サックスがいないカルテットバージョンです。1964年のライブなので、ショーターが参加しての直後のライブですね。
なんと1曲目は「枯葉」です。ロン・カーター、いろんな変な音を使ってますね。まさに真骨頂といえるでしょう。
そうそう、トニー・ウィリアムスは若干19歳です!
https://www.youtube.com/watch?v=l_T14jAkj2w
こちらは1967年のライブ。ショーターが参加して3年が経ちますので、メンバー同士のコンビメーションも最高ころではないでしょうか。まあ、この翌年には、ロン・カーターは抜けてしまうのですが。
どちらの演奏も、本当にとがってるし、かっこいいし、グルーブしています。
そして、マイルスの存在があるおかげで、もうただならぬ緊張感が漂っています。
いわゆるジャズのユニットとしての、ある意味、頂点の形を造ったユニットだと、僕は思っています。
ではそのロン・カーターのベースの特徴について、僕が思うところを書いてみたいと思います。
まずは以下の音源を聞いてみてください。
これは、この記事に関連して付けた譜面(有料となっています)の元音源です。
これは、1982年に発表された「Wynton Marsalis」という、いまやジャズトランペッターの神様のような存在になったウィントン・マルサリスのデビューアルバムに収録されているテイクです。
曲名は「Hesitation」
循環というタイブの曲ですが(詳しくは、「ジャズ入門講座伴奏編第6回」をお読みください)、ピアノレスで演奏されているだけに、ロン・カーターのベースラインがとても良く聞き取れます。
編成は、
Tp:ウィントン・マルサリス
Ts:ブランフォード・マルサリス
Bs:ロン・カーター
Dr:トニー・ウィリアムス
メンバーを見ただけでも聞きたくなりませんか?
しかも循環を演奏しているということで、これはジャズベーシストなら必聴の音源かと思います。
この演奏を聴いてわかってもらえると思いますが、ロン・カーターの特長を挙げると、大きく、次の3つが挙げれると思います。それは、
1)音色
2) グルーブ感
3)ラインのユニークさ
ではそれに関して、解説していきましょう。
1)音色
ロン・カーターといえば、70年代、彼がCTIというレーベルから出ている多くのアルバムに参加していたときの音色が最も特徴的かと思います。
それは、アコースティックベースらしからぬ、といっていいと思うのですが、ピックアップで拾った音を中心にした、かなりエレクトリックな音です。
この当時、アコースティックベースに関しては、その音をピックアップで拾って、それをアンプで再生するという、ある意味、革命的な技術の進化が起こったのだと思います。
それまでは、アコースティックベースの音といえば、マイクで拾って、会場にあるスピーカーで再生するのが精一杯。というか、それ以外の方法はなかったでしょう。
ですから、おそらくベーシストはもちろん、一緒に演奏する他のプレーヤーにも、すくなくともジャズクラブやホールでのコンサートでは、ベースの音はほとんど聞こえていなかったはずです。
もちろん、ビル・エバンス・トリオのバンガードでのライブのように、ピアニストもドラマーも、本当にささやくような音量で演奏してくれるならば、ベースの音も聞こえたかと思います。
ですからスコット・ラファロのように、高音域でバリバリ弾くというスタイルも成立したのでしょう。
しかしこのマイルス・バンドのように、トランペットやサックスが猛烈にブローし、それをさらにあおるかのように、ドラムスがバシバシぶっ叩くという状況では、ベースの音など、たとえマイクで拾っていたとしても、少なくともその細部にわたって、正確に何を弾いているのかが判る程度には、聞こえるはずもなかったと思います。
メンバーみんな、少なくともベーシストは、大きなストレスを抱えていただろうということは、容易に想像できます。
実際、マイルスバンドの映像などを見ていると、ロン・カーターはマイルスのすぐ後ろにいますが、トニー・ウィリアムスは、その二人から3メートルほど離れたところにいるようなものもあります。
これでは少なくとも、トニー・ウィリアムスには、ロン・カーターの音はほとんどといっていいほど、聞こえていなかったでしょう。
そんな全時代の状況を画期的に変えたのが、ベースのピックアップとアンプの登場です。
そして70年代に入って、そのことが一気に進んで、ベースの音量の問題が解決され、ベースの演奏スタイルそのものも大きく変わるようになったのだろうと思います。
その当時現れたベーシスト、例えばエディ・ゴメス、バスター・ウィリアムス、ジョージ・ムラーツ、ミロスロフ・ビトウス、セシル・マクビーといったベーシスト達は皆、ピックアップとアンプに大きく頼った音色となっていますが、その先駆けを作ったのが、このロン・カーターではないかと思います。
この「Hesitation」の音も、かなりアコースティックではありますが、それでもピックアップで拾った、エッジのある音色が、かなりマイクのそれとブレンドされていることがおわかりでしょうか?
ですが80年代の中頃からは、ほとんどのアコースティックベース奏者の音は、そういった音色はあまりに行きすぎた反動から、現在に至るまで、少なくとも録音された音は、よりアコースティックな音色に戻る傾向があります。
ロン・カーターの音も、このウィントンのアルバム以降は、70年代のあの独特の音色から、また60年代の、アコースティックな音に戻ったようですが、いずれにしても、70年代、ロン・カーターがもっとも活躍したときの音色は、本当に独特でしたし、その音がまた、彼の独特のフレージングを、さらにユニークなものにしたと言っていいと思います。
2) グルーブ感
彼のグルーブ感、特にマイルスバンドの頃のそれは、本当に心地よいし、ご機嫌なスピード感があります。もちろんこれはトニー・ウィリアムスに負うところも大きいでしょうが、でも、このウィントンの音源を聞いていただいても判るように、それまでの、レイ・ブラウンやポール・チェンバースのそれとはかなり違っていて、とても鋭角的でスピードがあるように、僕には感じます。
それはでも、次に触れるように、ラインにおける、彼独特の音の選択にも大いに関係していることかと思います。
3)ラインのユニークさ
マイルスバンドにおける彼のラインのユニークさは特筆すべきものがあり、その一つは、僕がそれをあえて「ロン・カーター方式」と命名するくらいのものです。
それは専門的にいうと、ルートの音に、5度と9thの音を絡ませ、その3つの音を中心に、1小節に4つの音から成るウォーキングラインを構築するという方法です。
それは、彼が好んで、ラインにそういう音遣いを選んだのか、あるいは曲があまりに難解なので、やむを得ずそうなったのかは判りません。というのも、当時のマイルスバンドの曲は、本当に難解なコード進行のものが多く、それまでのアイデアではベースラインがうまく構築できないからです。
が、このウィントンの音源を聞くと(そして先ほどの1964年のコンサートの「枯葉」を聞くと)、やはり彼は独特のハーモニーセンスと、コード進行に関する豊富な知識があることがよくわかります。
そういったものを駆使しながら、様々はリハモナイゼーションなどを加えてラインを作っているということがよく判ります。
このウィントンの音源の「循環」という曲のコード進行においては、普通に演奏すれば、実に普通のサウンドになってしまうのですが、ロン・カーターのそれは、随所にユニークな変わったラインが出てき来ます。
こういったアイデアは、やはり彼独特のものといえるでしょう。
とにかくロン・カーターは、それまでのベーシストとは全く違った独特のサウンド、ラインなんですが、そのことは彼のソロにもいえます。
メロディアスなアイデアというより、無機質な、しかもリズミックなソロです。
あんなアプローチをするベーシストは、やはりそれまでに一人もいなかったといえるのではないでしょうか?
さて、音楽全体のことで言うと、マイルスバンドのサウンドの流れをそのまま引き継いだのが、V.S.O.Pですね。
基本は、ハービーのピアノ、ロンのベース、トニーのドラムスからなるピアノトリオに、その時々の一線のフロントプレーヤーが入るというものです。
当初はマイルスの代わりに、トランペットにフレディ・ハバードが入っていましたが、1977年のライブ・アンダー・ザ・スカイでの、ショーターとハバードのフロントによるV.S.O.Pの演奏は伝説となっています。
僕が大学生のころに、ウィントンとブランフォードの二人がフロントになったV.S.O.Pを見にましたが、こちらも凄かったですね。
まさに、今回譜面を掲載した、ウィントンのデビューアルバムが出た頃の来日かと思います。
そう、ウィントンの日本デビューだったと思います。
ロン・カーターに関して、マイルスバンドの事ばかり書きましたが、実は彼の演奏でもう一つ、僕が大好きなのは、ギタリストのジム・ホールとの一連のデュオのアルバムです。
特にライブでの、「Alone Together」はお気に入りのアルバムです。
こちらの方では、実にオーソドックスな演奏になっていますが、それでもラインやソロには、独特の「ロン・カーター節」が出ていて、はやり彼のユニークな発想が、随所にちりおばめられています。
もともとは、幼少の頃からチェロを演奏し、本当にクラシックのチェリストになりたかったというのは、その後の彼のプレイスタイルと聞くとちょっと驚きですね。
どこでどうなって、こんな独特のスタイルが形成されたのかはよくわかりませんが、いずれにしても、独自の音色とスタイルを確立し、まさにジャズのある時代を支えたベーシストであることは間違いありません。


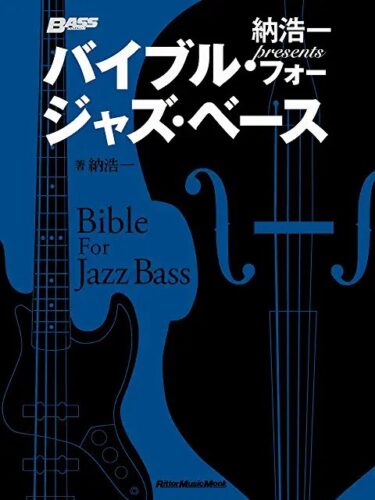 【新刊】【BOOK】納浩一presents バイブル・フォー・ジャズ・ベース
【新刊】【BOOK】納浩一presents バイブル・フォー・ジャズ・ベース